窪田 新之助(取材・文)
- Profile
- 福岡県生まれ。ロボットビジネスを支援するNPO法人RORobizyアドバイザー。著書に『日本発「ロボットAI農業」の凄い未来』『GDP4%の日本農業は自動車産業を超える』(いずれも講談社)など。近刊は『データ農業が日本を変える』(集英社インターナショナル)。
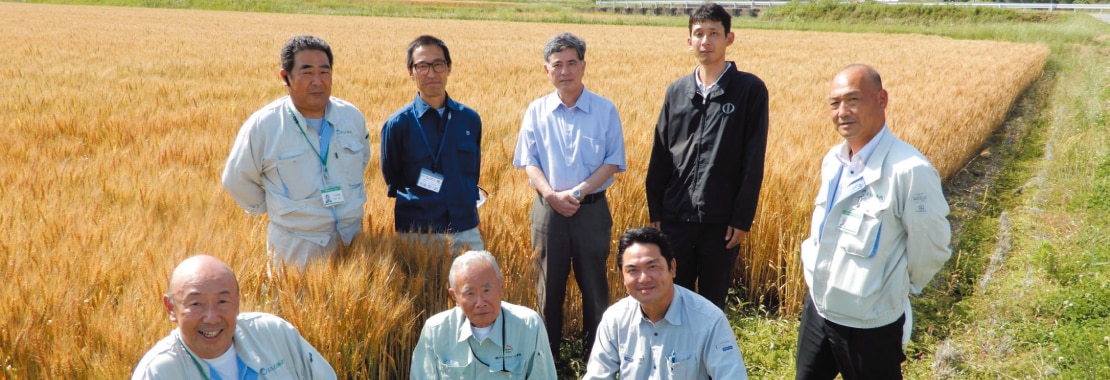
総務省統計局の「家計調査」(二人以上の世帯)によると、2014年から18年まで5年連続で、1世帯当たりのパンの支出額が、コメの支出額を上回っている。いまや日本人はコメよりもパンをはじめとした小麦の加工食品を多く食べるようになった。それなのに、その自給率は12%(2018年度)とじつに低い。コメの消費が落ちる一方で国産小麦の需要は確かにある中、生産側は「捨てづくり」という姿勢のままでいいのか。小麦は食品加工業者や小売業者、飲食店などと連携して需要に合った生産をすることで、水田農業経営の基盤をなす作物になるのではないか。そうした問いを抱いて兵庫県たつの市を訪ねた。
「うちの経営は小麦と大豆で成り立っているといっていい」
こう語るのは、兵庫県たつの市の集落営農法人、㈱グリーンファーム揖西の代表・猪澤敏一さんである。同社は五つの集落営農組織が合併した会社で、経営耕地面積は120ha、コメや小麦、大豆などを作っている。「はっきり言ってコメで入ってくる分(=収入)は経費でほぼ消えていく」。
猪澤さんの言葉は、国産小麦といえば「捨てづくり」という感じが強い中、異例といえるだろう。これに関しては、過去に国産小麦を積極的に扱うある食品加工会社の代表に取材した際に聞いた次の一言を思い出す。「農家に尋ねてごらん。自分の小麦が最終的にどう使われているのかって。ほとんどの農家は判らないと思うよ。硬質小麦と軟質小麦の違いも知らない農家も多いから。それだけ農家は小麦には無関心なんだよ」
その後の取材でこの言葉は実態を適確にとらえているのではないのかと感じるようになった。

グリーンファーム揖西も2000年ごろまでは小麦を収益を得る作物としては位置付けていなかった。それが一転したのは、小麦の最終的な供給先であるヒガシマル醬油が1998年、醤油の原料となる小麦をすべて国産に切り替えたこと。これを機に県やJAなどの力を借りながら需要に応じた小麦づくりを始めることになった。
ヒガシマル醬油は見た目の色が薄いことが特徴である薄口醤油の国内最大のメーカー。同社製造部アドバイザーの中田佳幸さんに全量国産化を決意した理由を聞いた。
「より安全・安心を求めて国産にした。また、外国産に依存していると不測の事態で原料が入ってこなくなる恐れがある。安定して調達するには国産、できれば地場産でまかないたかった」
国産小麦といっても何でもいいわけではない。同社が重視したのはタンパク含有率が13.5%以上。というのもタンパクは分解されると旨味成分のグルタミン酸になる。つまりタンパクが多いほど旨味が増すことに加え、色が薄くなる。
だからタンパク値が高い強力系の小麦を手に入れたい。ただ、当時は兵庫県の奨励品種の中に該当する性質を持った強力系の品種はなかった。そこで当初は北海道産の強力小麦を主力に使い始める。

一方で品種についてはアンテナを張り巡らしながら、試作を繰り返してきた。ただ、なかなか思うような品種に出会えなかった。そんな中、強力系よりもさらにタンパク値が高い品種が育成されたという情報を全国でもいち早く手にする。それが農研機構・北海道農業研究センターが開発した「北海261号」、いまの「ゆめちから」だ。
この品種が従来と全く異なるのは「超強力粉」という概念を打ち出したこと。それを理解するには小麦の種類と用途について知っておきたい。
小麦粉の種類はグルテンの量に応じて強力粉、中力粉、薄力粉に分けられる。このうち国産で多いのはうどんやお好み焼きなどに向く中力粉。かつての日本人にとって小麦の加工品といえば、中力粉を原料とするうどんやそうめん、お好み焼きなどの「粉もの」だった。強力粉や準強力粉を原料とするパンや中華麺を日常的に食べるようになったのは戦後。しかも外麦に依存する産業構造が出来上がっていったので、あえて強力粉になる品種を国内で開発する動機がなかったわけだ。パン用小麦の自給率が低い理由の一つがここにある。
この状況に風穴を開けたのが農研機構・北海道農業研究センターが2007年に開発した「ゆめちから」。「強力」以上の「超強力」であるこの粉を、国産で多い中力品種の粉と混ぜて使うことで、中力粉の生地の弱さを改善し、パンに利用できる。ちなみに北海道向けに開発されて同地で普及していった「ゆめちから」だが、じつは先行して試作したのは、ヒガシマル醬油と取引のあるグリーンファーム揖西らたつの市の集落営農組織である。


ヒガシマル醬油やJAなどから「ゆめちから」の生産を打診されたグリーンファーム揖西がこの品種で注目したのは収量の高さ。収量が高ければ、販売数量が上がるだけではない。「畑作物の直接支払交付金には「数量払い」と「面積払い」がある。このうち水田で作付けした場合でも対象になる「数量払い」は文字通り取れるほどに交付金が増えていく。
さらに水田転換畑で作付けする場合、「水田活用の直接支払交付金」の対象となり、転作するごとに10a当たり3万5000円が付くこと。それはほかの水田農業の経営体も同じ条件である。
2019年産では兵庫県における小麦の平均収量が10a当たり274㎏だった中、グリーンファーム揖西は「ゆめちから」で530㎏をあげ、収入は同10万円ほどとなった。もちろん、これだけの収量を上げるのは品種の力だけではないことは言うまでもない。その秘密はほ場にある。
6月上旬、猪澤さんに収穫間際のほ場を見せてもらった。一見して雑草や湿害にやられた個所はなく、豊作に違いないということがすぐに分かる。2019年産の収量を超えそうな気配を漂わせている。
ほ場を少し見ていると、努力のたまものであることにすぐに気づく。ほ場の周囲には額縁明きょの跡がしっかり残る。排水対策はこの額縁明きょに続いて弾丸暗きょを造る。水はけが悪いほ場に限って格子状に仕上げる手の込みようだ。播種する一週間前から土の表層30cmにチゼルプラウをかけ、播種の直前にはロータリーで10cmと浅く耕す。これによって土の表面は細かな土が、さらに深くはごろごろした土が層をなす。水はけがよくなり、発芽率が向上するそうだ。ここまで徹底して排水対策をするのは全国でも珍しいだろう。
猪澤さんによれば、もともとほ場は粘土質で「小麦ができない土地」だったそうだ。以上のような作業を続けるうちにチゼルプラウで有機物がすき込まれ、土の質が変わっていった。「俗にいう『畑土』になり、適度に保水力や保肥力のあるほ場に生まれ変わった」と証言する。
そのほか基本的な作り方は栽培マニュアルに依拠する。これはヒガシマル醬油と同社に小麦原料を卸す高田商店、県農業改良普及センター、JAが連携して作っている。
ここで強調したいのは、一連の関係者は小麦の品質と収量を高めるため、毎年さまざまな実験を繰り返していることだ。目下注力しているのは施肥の時期と量について。タンパク値を高めることと、倒伏させないことを両立させるためのギリギリの線を見極めている。このほかタンパク値を高める尿素の散布にかかる手間を減らすため、赤かび病を防除する薬剤にまぜて散布することも試している。
こうした実験の成果はその都度栽培マニュアルに反映する。たつの市ではグリーンファーム揖西に続いて7つの集落営農組織がこの栽培マニュアルに基づいて「ゆめちから」を作り、すべてJAを経由してヒガシマル醬油に卸している。現在、ヒガシマル醬油の小麦の年間使用量は6000トン。このうち2000トンは兵庫県産でまかなえるようになった。残りは北海道を中心に国産を使っている。


栽培技術についてもう一つ強調したいのは、たつの市集落営農連絡協議会がそれぞれの集落営農組織のほ場を巡回する研修会を定期的に開催していることだ。ほかの集落営農法人の作り方のどこが優れているのか、逆にどこが劣っているのかを見聞する。その際に役立つのはヒガシマル醬油が購入して運用しているドローンによるほ場の画像。集落営農組織が互いに小麦の出来の違いを見比べ、改善点があれば互いに遠慮なく指摘する。
研修会を開いたことでまず変わったのは栽培技術のレベル。猪澤さんは証言する。「(研修会では)互いに褒めたり批判したりする。ここのほ場は草が生えてないけど、どうしてなのかと勉強するわけ。それを繰り返しているうちに、わずかなことだけど段々と改善されてくる。かつては草が多かったり水がたまっていたりするほ場が結構あったけど、いまはほとんどない。(研修会が)集落営農の経営に利益をもたらしているなと感じていますよね」。
加えて集落営農組織が互いに仲良くなったことも利点に挙げる。
「もともとそれぞれの集落営農組織は仲良くなかった。それが巡回することで気心がしれて、自分たちの経営だけではなく、たつの市全体の農業をどうしたらいいかということまで話し合うようになった」
具体的には集落営農組織を「二階建て方式」から「三階建て方式」に発展させることを考えている。「二階建て方式」とは集落営農の生産部分の法人化。「三階建て方式」とは全国的には聞きなれない言葉だが、猪澤さんによれば、たつの市集落営農連絡協議会に所属する集落営農組織が自らの組織を超えて互いに出資し合って株式会社をつくり、資材の共同購入や共同利用など互いの利益になる事業を運営することだという。米価が下がる中、ほかの集落営農組織に高収益作物として小麦や大豆の作付けを促し、営農を支援することも検討している。
県やJAなどの力を借りながら醤油に向く小麦づくりに邁進するグリーンファーム揖西をはじめとするたつの市の集落営農組織。その過程で「ただの百姓から事業家百姓になってきた」と、猪澤さんは認識している。私はこの発言に、猫の目農政とそれに身をゆだねて「捨てづくり」を続ける「百姓」への批判が込められていると感じた。
国内では「水田活用」と言われながら、実態としては生産調整の手段に陥ってきた小麦の生産。そんな状況にある小麦が「戦略作物」であるはずはない。打開策のヒントはたつの市の取り組みが教えてくれているはずだ。
そうはいっても「うちは小麦に向く土壌ではないから取れない」という声が聞こえてきそうである。それはグリーンファーム揖西も同じである。重粘土壌だったところに有機物をすき込んだり排水対策を徹底したりして「畑土」に変え、小麦が作れるようにしてきた。10a当たりの平均収量が530㎏を達成した裏には、そうした営農上の着実な努力があったことを最後に言い添えて本稿を締めたい。
