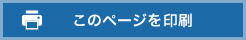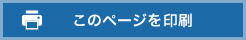助成先一覧
<研究テーマ>
持続的農業につながる作物光合成活性のリアルタイムモニタリングカメラの開発
- 研究の概要
- 大規模農業においてICTを利用し作業の効率化を図るためには、作物の生育状況をリアルタイム、かつ面的に把握することが肝要である。リアルタイムに評価するシステムを確立するために、これまで開発してきた計測カメラ本体・ソフトウェアを基に、不足していたクロロフィル蛍光(SIF)と光合成情報(葉の光合成活性・色素)の関係についての野外実証を行う。
- 研究者 :
- 北海道大学 農学研究院 加藤 知道 准教授
- 助成期間:
- 2017年4月1日~2018年3月31日
- 助成額 :
- 180万円
研究の成果についてうかがいました
- Q1:完了報告書の「今後の予定」に記載された、計画通りの展開はできましたか?
-
助成期間中に観測した分光放射データから計算したクロロフィル蛍光SIFでは正常な値が出ていなかったため、翌年度に処理区を6つに増やして再挑戦した結果、窒素施肥量が低から高になるにつれてSIFが高くなり、光合成活性を反映していることが明らかになりました。一方、病虫害検出やドローン計測については現在も検討継続中です。
- Q2:助成研究で得られた成果は、現在の研究活動にどういった形で活かされていますか?
-
翌年度(2018年)に発展させた野外SIF計測と、それを再現する3次元放射伝達モデルによるシミュレーションによって、窒素施肥段階だけではなく、条を立てる方角にも依存してSIF放出強度が変化することが明らかになってきましたので、それらの成果をまとめ、現在国際学術雑誌へ投稿準備中です。
(2021年11月ヒアリング)
- >助成研究のその後 一覧に戻る