上久保 和芳 氏
長野県 諏訪農業改良普及センター 技術普及係 主査
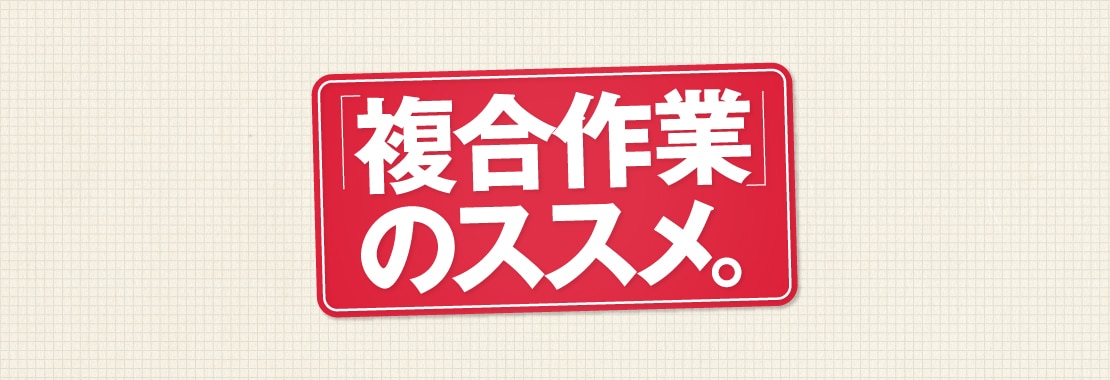
複合作業には、天候の影響を受けやすい日本における農業の、適期作業の実現はもちろん、トラクターの踏圧によるほ場の踏み固め低減や、燃料の削減、作業ごとのトラクターやオペレータの確保の軽減など、さまざまなメリットがあります。『適期作業のための時間短縮術』の中でもご紹介したこれらのメリットですが、実はそれだけではなく、「複合作業だから」実現したプラスのメリットがあるのです。
そこで今回は、そのプラスのメリットも含めた事例をご紹介。ぜひ、複合作業に挑戦されてはいかがでしょうか?
従来は、耕うん・うね立て・播種・施肥など、4つの作業が必要でした。「複合作業」は一度の作業でOKです。

連続する2つの作業の間で雨が降ってしまうと、もう一度やりなおさなければならない場合もあります。作業に適した好天が、連続して続かない場合が多い日本において、適期に作業できることは大きなメリットになります。
①作業可能な日は8日間のみであり、適期作業が難しい場合がある。
②複合作業での1工程作業により、限られた日数でも作業が完了できる。
③苗の植え遅れもなく、適期作業、均一作業で安定生産に貢献。

トラクターの燃料の削減や、オペレータの確保からの解放による経費節減はもちろん、複数の作業を1人でできることは、作業人数の少ない経営体系では特にメリットとなります。

トラクターでほ場を何度も走行すると、ほ場を踏み固めてしまいます。複合作業では、トラクターがほ場に入る回数が減るので、ほ場の踏み固めが低減できます。
うね立てと同時に畦内に施肥することで、全層施肥に比べ大幅な減肥を実現。畦内施肥は、まさに複合作業から生まれた減肥技術です。

土を破砕して持ち上げると同時に、後ろのロータリーで砕土耕をするため、土がやわらかく、後作業機の爪への負担が軽減されます。そのため、爪の寿命が伸びるのです。

耕うん後すぐに播種をするため、雑草が生える前に播種ができ、除草剤の削減につながります。また、播種床が均平なため発芽が揃い、高品質な作物づくりになります。
みずみずしさやシャキシャキした食感、香気が魅力のセルリー。生産高全国1位は長野県ですが、中でも夏場のセルリーは原村を中心とした諏訪地域が一手に担っており、シェア90%以上を誇ります。
そんな管内で畦内施肥技術と複合作業機が完成。実証試験で狙い通り、減肥、省力化、コスト削減などの効果が証明され、同機を導入するセルリー生産者が相次いでいます。

長野県有数の観光資源である八ヶ岳と諏訪湖の間、標高900~1300mの高原地帯に広がるこの地域では、冷涼な気候と降り注ぐ陽光、八ヶ岳からの豊かな伏流水、肥沃な土壌に恵まれてセルリーを主力に高原野菜の生産が盛ん。諏訪管内でのセルリー農家は85戸、栽培面積は145ha。そのうち、原村は52戸、126haの面積を占める主産地です。
ただ、セルリーは生育期間が長いうえ窒素成分を好むという特性から肥料が多く使用されており、下流にある諏訪湖の水質への影響が懸念されていました。
そこで平成16年から県とJA信州諏訪が連携して、環境への負荷軽減を目的にした減肥栽培技術の開発に取り組んできました。特に減肥に有効な畦内施肥技術に力を入れ、セルリーの吸肥特性に合わせた肥効調節型(緩効性)専用肥料「らくセル」も開発。それに合わせて、畦内施肥をはじめうね立て、土壌消毒、マルチングを同時に行う作業機の開発と実証試験が行われました。
トンボ会メーカーの協力を得ながら作業性や効率を良くするための改良を重ねていき、複合作業機が完成しました(図1)。

歩行型管理機に、土壌消毒機とうね立てマルチ同時作業機を使用した複合作業機を試作。作業性向上・作業回数減少をめざす。

本機を乗用管理機に変更。肥料散布精度の向上と、オペレータの疲れの軽減をめざす。
肥料散布装置を改良した乗用管理機用の複合作業機を開発。実践的利用から、より一層の作業性向上をめざす。

トラクター用の複合作業機を開発。使いやすさや安全性向上などをめざす。

トラクター用の改良型複合作業機完成。
この複合作業機での本機はヤンマートラクターGK13(13PS)。
その前部に施肥機と土壌消毒機、そして後部にはロータリー、うね立て整形機、マルチャーが装着されています。
トラクターを走らせると、施肥機が肥料を畦内に確実に散布し、ロータリーが土を撹拌しながら土壌消毒剤を注入し、うねを立てマルチを張っていきます。従来はこの複数工程を別個に行っていましたが、同時に作業してしまうスグレモノです。

では、この複合作業機によって実際にどれくらい効果があるのか、実証ほ場での試験と導入農家への聞き取り調査の結果から詳しく見てみましょう。
慣行の全層施肥では根が吸収できない所までほ場全面に肥料をまくのに対して、この機械では畦内に散布します(下図)。そのため無駄にまかれていた分が節減できます。
全層に施肥後、うねを立てる。

畦内に施肥しながら、うねを立てる。

そこで減肥率の目標を3割に設定して試験しましたが、順調に生育し収量や品質に差がないことが確認されました。導入農家も同様で、3割減らしても2L比率が7~8割を確保できました(表1)。
| 生産者 | 基肥削減率(%) | 調製重(kg) | 2L比率(%) | 作業機の評価 | H25年減肥率 (予定)(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業性(※1) | 疲労度(※2) | |||||
| M氏 | 60 | 1.60 | 20 | B | 減少 | 20 |
| K氏 | 30 | 1.73 | 30 | A | 大きく減少 | 30 |
| G氏 | 30 | 1.90 | 70 | B | 減少 | 30 |
| Y氏 | 30 | 2.04 | 80 | B | 大きく減少 | 30 |
| N氏 | 25 | 1.82 | 55 | A | 大きく減少 | 30 |
| U氏 | 20 | 1.84 | 65 | A | 減少 | 25 |
(諏訪農業改良普及センター資料より)
車速は約1.3km/時で、歩行型と比べておよそ2倍速い。その上、従来別々に行っていた施肥、うね立て、土壌消毒、マルチングが一度に行えることで、半分以下の時間で済みます。
特に4~5月はハウスでの育苗と畑への植付けが重なるため、時間短縮の効果は大きくなります。
上記の時間短縮に加えて、傾斜地や凹凸のある畑でもトラクターだと労力が要らず、疲労度が軽減されました(上表1)。
慣行の施肥量と比べて、3割減肥の場合、肥料代が10a当たり約1万5000円削減できます。さらに燃料代も減らせるので、一層の経費低減が図れます。
機械を何回も走らせなくて良いので、土の踏み固めが最小限に抑えられます。
以上の好結果を受けて、村内85戸のセルリー農家の間で同機への関心が高まり、平成26年5月までに9戸(内1戸は富士見町)が導入。稼働面積は22.6haに及びます。
ちなみに機械の導入に当たっては、23年度長野県単独補助事業や24年度JA信州諏訪 農業振興・生産拡大補助事業が用意され、導入を加速させました。
畦内施肥技術の取組みを中心になって進めてきた、長野県諏訪農業改良普及センターの技術普及係・上久保和芳主査に、今後の可能性などをうかがいました。

長野県 諏訪農業改良普及センター 技術普及係 主査
畦内施肥技術の取組みに、上久保主査は、「平成19年に機械の開発に着手して以来、課題が出てくる度にJA信州諏訪をはじめ農業試験場やトンボ会メーカーなどと連携して解決していきました。現地に即した畦内施肥技術が生産者にもメリットとなる技術として導入が開始され、嬉しいですね」と目を細める。
初期投資はかかるが、これまでの肥料「セルエース」から、新しく開発された肥料「らくセル」に変更して3割削減した場合、2.3ha以上の面積をつくれば肥料代削減分で減価償却額が捻出でき、経営にプラスが出てくるだろうと試算する。また、セルリーに限らず同様の作業が必要な作物でもこの技術は応用できるという。
「機械は出来上がりました。あとはいかに普及させるかです。昨春から栽培技術情報誌『セルりん童子』を発行してきたのも、農家の理解を深める上で効果を上げています。今後も、地力や条件が異なる畑ごとに減肥率を検討したり、専用肥料を低温期に使用する際の留意点や枕地対策などを示し、普及に努めます」と意欲を見せる。他産地、他作物からも注目されている新技術、今後の展開を見守っていきたい。
実際に複合作業機を導入した生産者の方々に、導入した狙いや実際に使用した感想をうかがいました。

経営規模:セルリー4.0ha・水稲1.8ha
労働力:ご夫婦、息子さん・常雇用1名
導入して3年目になりますが、一番いいのは肥料が少なくて済むことです。不要な所には肥料をまきませんから相当減らしても大丈夫ではないかと考え、4割減に挑戦しました。それでも生育や収量、品質に問題はなかったですよ。肥料を10袋使っていたのが6袋で済む勘定です。
肥料代の差額を計算すれば機械代は十分に出ます。長い目で見れば経費が減り、経営に余裕ができます。JA・柳沢輝佳係長さん達の営農指導も心強いですね。
疲れないのも嬉しいです。以前、土壌消毒やマルチングは歩行型管理機で作業していましたが、へとへとになりました。今はトラクターだから力は要らないし、上り坂でも滑らなくて大助かりです。
春は複数の作業に追われ、気分的に焦るし休む間もなかったのが、複合作業で時間に余裕ができ、体も気持ちも楽になりました。空いた時間はあとに備えて休みます。マルチをかけたら1~2週間後には苗の植付け。それが5月から8月中旬まで続きますからね。


経営規模:セルリー3.5ha・水稲4ha
労働力:ご夫婦・娘さん
作業効率の高さが一番の魅力です。
定植前に畑の準備をする作業はどれも面倒だし、時間も取られます。それがトラクターを1回走らせるだけで全部やってくれるのですから、有り難い限りです。疲労度も大きく軽減できました。トラクターの水平制御機能も効果大です。傾斜地が多いのですが、安定した作業ができます。
畦内施肥については、田植えの側条施肥と同様に、セルリーも畦内施肥は効果があるだろうと期待しました。
まず肥料が無駄になりません。以前は10a当たり40袋(窒素成分10%)使っていたのが、今は13袋(窒素成分23%)。それでも生育も収量も慣行と比べてそん色はなく、むしろ枝数が増え大株で格好もよく、日持ちもします。品質のばらつきもありません。専用肥料に変えたのもありますが、畦内散布により施肥ムラがなくなった効果も大きいと思います。
肥料だけでなく、土壌消毒剤も確実に畦内に入るのもいいですね。連作障害を防ぐために土壌消毒は不可欠ですから。


経営規模:セルリー4.9ha/米1.7ha・野菜30a
労働力:ご夫婦・息子さん2人・常雇用2名・出荷時のアルバイト2~4名
セルリーをつくり始めて30年以上、今では1日に350ケース出荷しています。JAセルリー専門部会では需要拡大に力を入れていますが、畦内施肥や複合作業機でより高品質なセルリーが省力、低コストで生産できれば消費も拡大するでしょう。
栽培は息子達に任せていますが、畑を預けたいという高齢の農家もおります。省力化で余裕ができる分、地域の要望を受け日本一の産地を守り発展させてほしいですね。

セルリーは手間がかかり栽培が難しい作物ですが、やりがいを感じています。環境に配慮して減肥栽培をするのは時代の流れですし、窒素が多すぎると病気が出やすくなります。どこまで減らすのが最適か、土壌診断を行ってうちの畑に合った減肥率を検討中です。
機械は今年購入したばかりで稼働時間は短いですが、スピードが速く楽。使いやすいように工夫しながら、最大の効果を発揮させていきたいですね。

